この本は、ビジネス分野で長年研究されてきた経営戦略論などの知見を、自身の生き方にも応用できるとした、とてもユニークな視点の本だった。
以下、書籍の文章を引用しながら、筆者の感じた点について述べていきたい。
「01パーパス 人生というゲームの「基本原理」を押さえる」に、人生の資本を3つに分けたうえで、時間軸をどのように配分していくのが良いかという点について、以下のように述べられている。
・時間資本を別の資本に変えるゲーム
スタートポイントは時間資本です。人生のステージの最初の段階、10代から20代にかけての「働き始めの時期」においては、スキルや知識といった人的資本も、信用や評判といった社会資本も、持っていないという人がほとんどでしょう。彼らが持っている資源はただひとつ、それは「ありあまる時間資本」だけです。
この時間資本を、良い学びを得られる「スジの良い学習」や、良い経験を得られる「スジの良い仕事」に投下すると、その時間資本は、知識・経験・スキルといった人的資本に転換されます。
出典:『人生の経営戦略』山口周
近年、「ワークライフバランス」「コスパの良い生き方」などが流行っているように思いますが、若いうちからライフ重視でやっていくと、年をとって40代、50代となってから結果的にワークもライフもバランスしないという結果になってしまう恐れがあります。
20代、30代の若いうちは多少ライフを削ってもワークに力点を置き、まずは人的資本を拡充させ、その人的資本を社会資本や金融資本を増やすために使っていくというのが良いと思います。
この辺りの人生の資本を「人的資本」「社会資本」「金融資本」にわけて配分を考えることが大事というのは、橘氏の『幸福の資本論』の主張にも通ずるところがありますね。
ポジショニング戦略を人生に応用するところでは以下の通り山口氏は述べています。
ポジショニング
「市場における価値」は「能力や知識の水準」ではなく、「需要と供給の関係」によって決まります。
言われてみれば当たり前のことだと思いますが、キャリアアップというと私達はつい資格取得などの知識獲得などに走り勝ちです。
当然成果を出すためには仕事に必要な知識を身につけるために努力することは大切ですが、そもそもの前提として、「どの場所(どの業種、どの会社、あるいは独立)」で頑張ることを戦略的に考え決めたうえで、能力や知識を身につけて、その場所で成果を出すという流れがとても重要だと改めて感じました。
最後に、イニシアチブ・ポートフォリオに山口氏自身の経験として、キャリアを考える際に考えたことについて印象に残ったので紹介します。
・イニシアチブ・ポートフォリオ
私は30歳を境にコピーライターとして・クリエイターとして自分の将来性に見切りをつけて電通を退社し、米国の戦略系コンサルティング会社に転職しました。
仕事はさすがに厳しく、連日、深夜まで働く日々が数年にわたって続きましたが、同時にやりがいもあり、また幸いにもウマの合う同僚にも恵まれ、30代の半ばの頃には「このままいけばパートナーになるのかなあ?」などとぼんやり考えていました。当然のことながら、当時は自分の時間資本のすべてを目先のコンサルティングの仕事と、その仕事で成果を出すための短期的な勉強のために投入していました。
しかし、そんなある日、上司に当たるパートナーの人たちのあまりの多忙ぶりを見るにつけ、ふと考えてしまったのです。それは「なぜコンサルティング会社のパートナーは、職位が上がれば上がるほど、忙しそうなのか?」「そもそも自分は10年後にこうなりたいと思っているのか?」という問題です。
悶々と考えた結果は非常にシンプルでした。それは「自分の時間を他人に売るというコンサルティングのビジネスモデルの構造上、自分の価値が上がれば上がるほど、機会費用が大きくなるかた」ということです。
出典:『人生の経営戦略』山口周
これは筆者のような公認会計士をはじめとする士業においても同様の問いが当てはまると思います。
自分の時間を切り売りするビジネスモデルがダメというわけではなく、自身の能力を日々向上させ、多くの経験を積み、クライアントにサービスを提供する業務は、社会にとってとても価値ある仕事だと思います。
ただ、死ぬ直前の方に聞いた後悔では、「もっと仕事をする時間を押さえておけばよかった」「友人や家族をもっと大切にすればよかった」というのが多いことも考えると、バランスが大事なのかなと思います。
もちろん、最初に述べたように若い時の短期目線だけでなく、長期的に人生を考えてのバランスですけどね。
本書を読んで筆者が考えたことは以上です。
自分の人生を考えるうえでとても示唆の多い本でしたので、気になった方は是非読んでみてください。

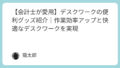
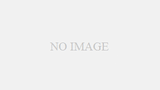
コメント